犬の耳血腫とは?原因・症状・治療法について解説

「愛犬の耳が腫れて心配」と思っていませんか?
大きく耳が腫れた状態が長く続くようであれば、耳血腫かもしれません。
今回は、そんな耳血腫の原因や治療法について解説していきます。
犬の耳血腫とは?

耳血腫(じけっしゅ)とは耳の内部にある軟骨の部分に血が溜まってしまった状態のことです。
この血が溜まることによって耳たぶの内側が大きく触れ上がるのが特徴です。
まず耳介、つまり耳の部分には軟骨があり、それを皮膚が包み込むことで形が形成されています。
そして軟骨と皮膚の間に血管が走っているのですが、その軟骨の部分に血液が溜まってしまうのです。
ですから基本的にはこの耳介の部分に血液が出血を起こすことで生じます。この点は原因の部分で改めて触れますが、垂れ耳の犬種に多い傾向が見られます。
犬の耳血腫の症状

先述したように耳血腫は耳介の内側に血液が溜まる状態のことです。
主な症状として、
などがあります。
このような症状が見られた場合には、耳介に腫れ・膨らみが生じていないかどうかをチェックするようにしましょう。
また、この耳血腫が厄介なのは単独で症状が現れるだけにとどまらず、外耳炎を併発しているケースも見られることです。
耳介の炎症が発生し、それにより耳血腫を発症することもあります。耳血腫の症状が見られた場合は、同時に外耳炎などの他疾患にも注意を向けましょう。
もし腫れ・膨らみといった典型的な耳血腫の症状が見られた場合には外耳炎を併発していないかどうかをチェックするのはもちろんのこと、逆に外耳炎の症状が見られた場合に耳血腫を併発する前の段階でしかるべき治療を受けさせることも重要です。
外耳炎の場合
などが挙げられるので、合わせて覚えておきましょう。
【関連商品】
犬の耳血腫の原因について

主な原因に関しては繰り返しになってしまいますが、
です。この点は人間の内出血と共通しています。
また、たれ耳の犬種である
といった犬種は耳血腫を発症しやすいため注意が必要です。
早い段階で治療を施さずに悪化させると耳が変形してしまう恐れがあるほか、不快感やかゆみからわんちゃんがイライラしたり、攻撃的になるなど性格・行動面で症状が出てきます。
見た目の変化で比較的察知しやすい病気ですから、耳の状態を日頃からチェックしましょう。
犬の耳血腫の治療法

治療法は溜まってしまった血液を外科的に除去する方法が一般的です。患部に針を刺したうえで血液を抜く作業を数回の手術に分けて行います。その間は通院が必要になるので飼い主さんは予定の確保なども必要になるでしょう。
ただ症状が進行した場合には針を刺して血液を抜くだけでは十分ではないことも多く、より外科的な施術が行われます。その場合は、メスを入れてより大きな穴を開け、血液を排除したうえで穴を塞ぐ方法で治療を行います。
さらにほかの治療方法として、
・血液の排液は行わず、インターフェロンを血腫ができた部分に注入する方法
・針で穴をつくって排液を行った上でステロイド剤を注入する方法
なども用いられています。
かかりつけ医の獣医さんとよく話し合い、費用や通院頻度など飼い主さんと愛犬にあった治療法を行いましょう。
犬の耳血腫の予防

耳血腫の予防法としては、
などに気をつけましょう。
予防に関しては上述のように外耳炎から進展することが多いのでまず外耳炎を予防することが第一です。
具体的には外耳炎の発症原因となる、
などに気をつけましょう。
また、衝撃が原因で出血を起こしてしまうことも多いだけに耳への物理的な衝撃を加えないよう気をつけることも大事です。
わんちゃんが耳をかく、頭を激しく振るなどの症状が見られた際はエリザベスカラーの着用などの対策を行いましょう。
【関連商品】
わんちゃんライフについて
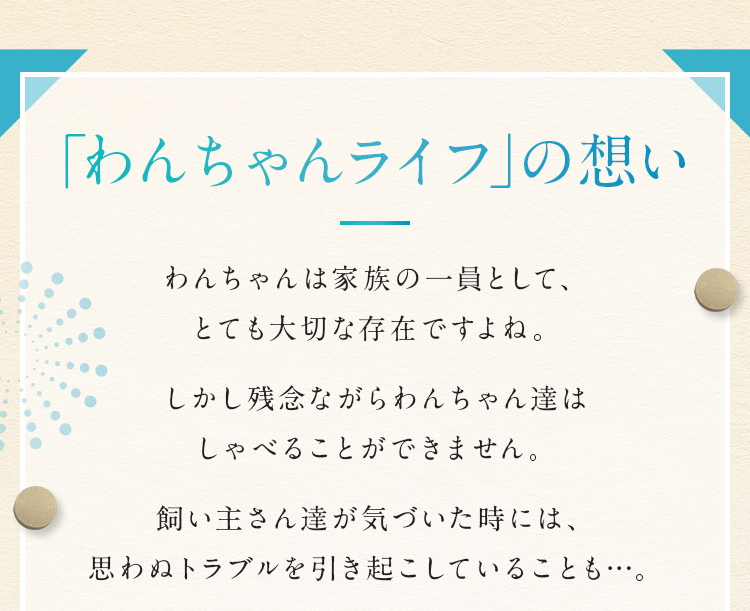
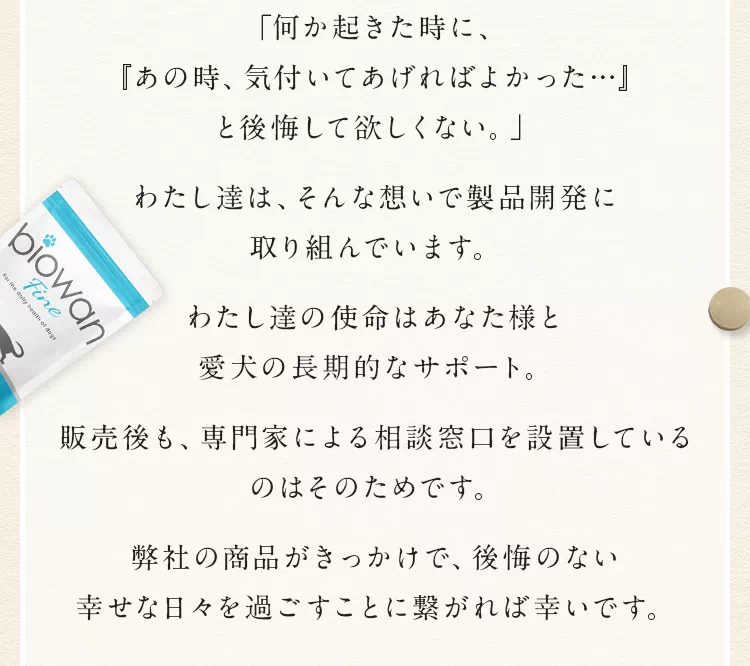


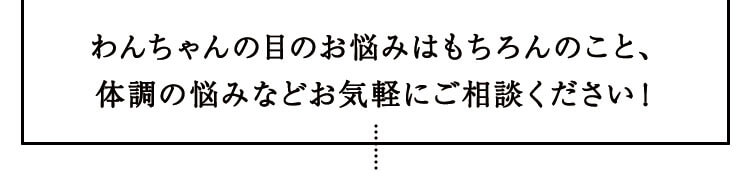

「わんちゃんライフ」では、HPよりドックフード・日用品・サプリメントなどの商品をお得に購入することができます。
500円OFFクーポンを公式ラインから取得し、ぜひご活用ください。
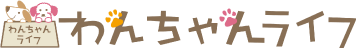



 ログイン
ログイン
 カート
カート
 お問い合わせ
お問い合わせ
 商品ラインナップ
商品ラインナップ
 カート
カート
 お問い合わせ
お問い合わせ

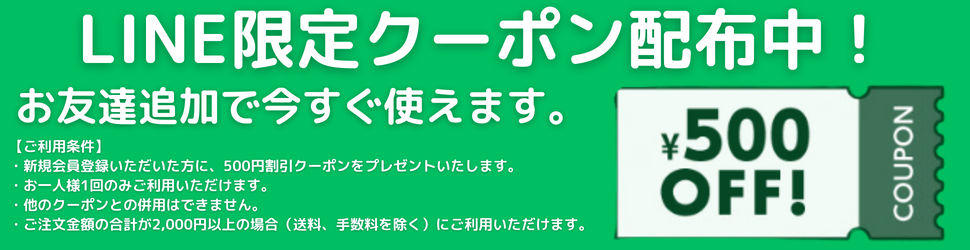
 ラインナップはこちらから
ラインナップはこちらから お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら