犬のおならが臭い原因とは?対処法についても解説

犬も人と同じように食事や排せつをします。もちろん、おならもします。
日頃愛犬と一緒に過ごしていて、おならの回数が多いと感じたり、おならが臭かったりした場合、いくつかの原因が考えられます。
今回は犬のおならの原因や対策について解説していきます。
犬のおならの原因とは?
消化器から排出できなかったガスが肛門から排出されることで、音が出たりニオイを発したりします。人間と同じように、犬もおならをします。おならの原因には様々なものがありますが、今回はその中でも主な4つを紹介します。
消化不良

食べ物が何らかの理由でうまく消化できない場合に腸内で腐敗し消化不良を起こすことがあります。
嘔吐や下痢などを伴う胃腸炎のケースがみられる場合もあります。
また、子犬や老犬などは、食べたものが消化しきれないということもおならにつながります。
早食い
特に、子犬世代に多いのですが、目の前にあるフードを瞬く間に食べきってしまう早食いが原因になることもあります。
フードと一緒に空気を飲み込んでしまうと、おならとして出てしまうことがあります。
おならが多いときは、おなかの張りが気になっていることもあるので、犬の食後の状況なども確認していきましょう。
空気を飲み込む

フードと一緒に空気を飲み込むこともそうですが、犬は時折浅い呼吸(パンティング)を始めることがあります。
この浅い呼吸の際に空気を飲み込んでしまうことがおならの原因として考えられます。
個体差もありますが性格上興奮しやすい犬や、パグやシーズーのような短頭種にパンティングの傾向がみられます。
心配はいらない状況ですが、空気を飲み込むことでおなかが張る症状を伴う場合も考えられます。
腸内細菌によるガス発生
ゆでた野菜を食べさせているという場合、食物繊維が消化しきれずガスが発生することも考えられます。
特に犬は食物繊維を消化することが苦手なので腸内にたまりやすくなります。
このほか、フードの影響によって腸内細菌のバランスが変わることもあります。
また、腸内細菌が代謝を行う際にガスを発生することもあるようです。
「犬のおならが臭う!」その原因とは

犬のおならが突然臭くなることがあります。
1~2回程度であれば、生理的なものととらえることができますが、明らかに異様な臭いがするといった場合は、その原因を探る必要があります。
気になることがあれば、獣医師に相談をしましょう。
フードが原因

フードの銘柄を変えた直後に、おならが臭うようになったというケースがあります。
タンパク質が多いフードは、臭いが強くなりやすいです。
また食物繊維が配合されているダイエタリーフードや、カロリーオフを意識してブロッコリーなどを食べさせているという場合も注意が必要です。
病気が原因
膵臓や胃腸といった消化器に直結する疾患が、おならの臭いの原因のひとつとして考えられますが、関節痛や椎間板ヘルニアというように動くたびに外的な痛みを伴う病気でもおならが臭くなる可能性があります。
痛みと苦しさを逃すために、パンティングをすることがあり、空気を飲み込むことがおならの原因になります。
膵臓の分泌異常や胃腸炎などの症状があると、口臭やおならの臭いが強くなる原因につながります。
おなら対策は自宅でできる!

おならの回数を減らしたいという場合や、臭いを避けたいという場合は、自宅でできる対策を施しましょう。
しかし、おならが多い場合には何らかの病気が隠されている場合があるので、愛犬の様子を注意深く観察しながら対処していきましょう。
フードの与え方や銘柄を変える
タンパク質が高めのものや食物繊維が多めのフードの場合、おならの回数の多さや臭いに直結します。
タンパク質が少なく配合されているものを中心にフードを変えていきましょう。
また、野菜を煮たものなどを与えている場合、量を少なくすることも一案です。
早食いをする犬の場合は、早食い防止用のフードボウルを使用してゆっくり食べてもらうように工夫しましょう。
空気の飲み込みも防げ、おならも少なくなるようです。
肛門腺絞りも併用しよう

肛門の周りに肛門腺と呼ばれる袋(嚢)があります。
肛門腺からはペーストもしくは液体の臭いがある物質を分泌します。
肛門腺は相手を識別するためのものと考えられていますが、おならの臭いにも直結しやすいので、定期的に肛門腺絞りをしてあげましょう。
月に1度程度、シャンプーのタイミングで絞ってあげるとよいでしょう。
まとめ
おならの回数が多い場合はさほど心配ありませんが、時折病気に直結することがあります。
回数や臭い、愛犬の状態などを細やかに観察し、気になるようであれば、獣医師に相談をしてみましょう。
わんちゃんライフについて
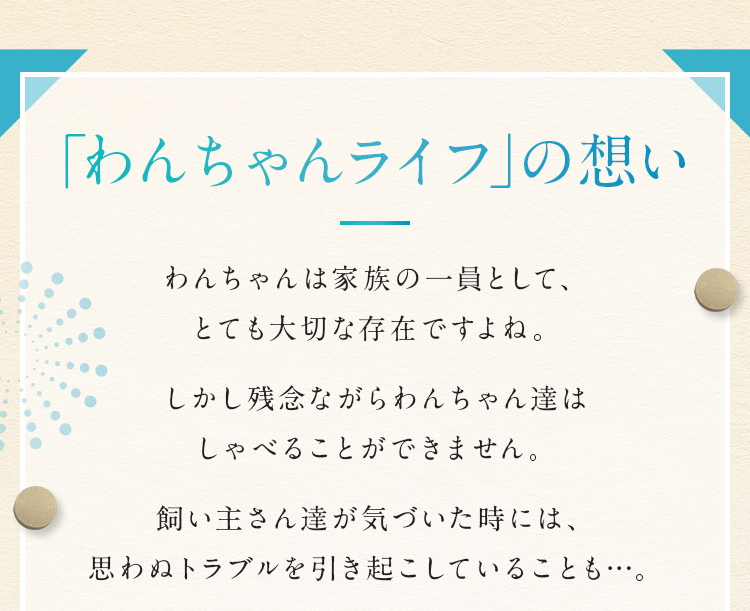
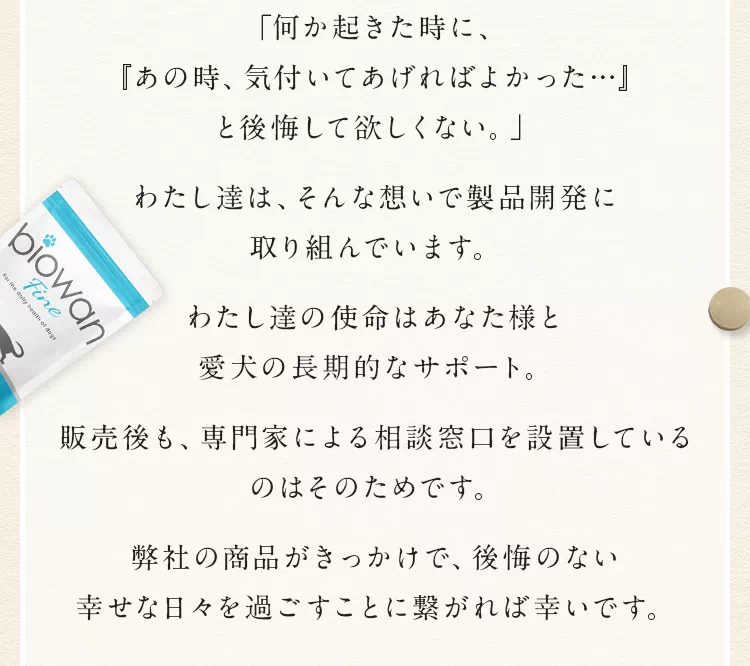


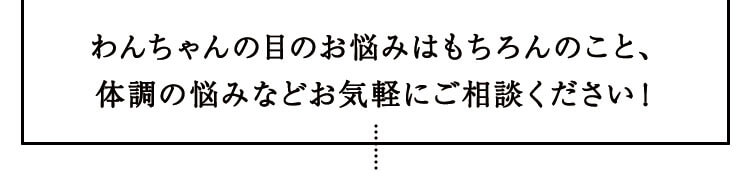

「わんちゃんライフ」では、HPよりドックフード・日用品・サプリメントなどの商品をお得に購入することができます。
500円OFFクーポンを公式ラインから取得し、ぜひご活用ください。
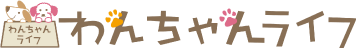



 ログイン
ログイン
 カート
カート
 お問い合わせ
お問い合わせ
 商品ラインナップ
商品ラインナップ
 カート
カート
 お問い合わせ
お問い合わせ

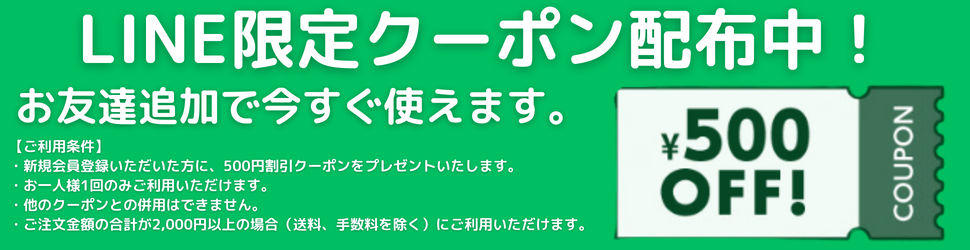
 ラインナップはこちらから
ラインナップはこちらから お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら